再利用による縁側改修工事
数年来、役員会で懸案事項となっていた本堂縁側の改修工事が完了した。今回中心的に使用したケヤキ材は、門徒さんのかつてのご自宅で柱として使われていたもの。これを製材して上手く取り付けできるか、宮大工の渡辺左一棟梁に相談した。すると、古材の再利用では思わぬところにクギがあるなどリスクがあるがやってみましょう、との回答。予算的にも特別会計内で対応できる。昨年末の総会で承認いただき、お彼岸までの完了で、とお願いした。
再利用のため、新しい製品での工事とは異なる点が二つある。まず、古材にある傷や不具合部分には埋木してある。また、全ての範囲をカバーできる材料量ではなかったため、周辺部分にはいったん取り外した既存板の中から適当なものを充てた。
傷もまた尊い味わい
古材が元々使われていた建物は、他所にあった客殿を移築し自宅利用した、と聞いている。お座敷があり、お寺の大きな行事等で控室として使われることもしばしば。中郷小学校に嶺北出身の新任教師が赴任した時の下宿先になったことがある。二階にある先生の部屋に遊びに伺い、ギターを聞かせてもらった五十年前の記憶がはっきりと残っている。
そんな懐かしい建物を支えていた黒光りした太い柱が大切に保存されていて、寄贈していただける。難しい工事を引き受けて下さる大工さんがいる…。今回の工事は営繕事業ではあるが、念仏の響きを確かめる尊い機縁といえる。謹んで合掌する次第である。パッと見たところでは気づかないが、数か所に施されている埋木。百年以上も前、雪にも地震にも耐えられる強度をもって刻まれた木組みの傷跡、丁寧な大工仕事の遺伝子である。棟梁がここは決して切り取って捨てるようなことをしたくない、とこだわったお気持ちを汲みとりたい。また、その建物の中では何世代もの時代をこえ、敦賀・中郷・古田刈という地域枠をこえて多くの先人たちが念仏申された。その歴史的営みの深さと重さ、温もりを足裏から感じたいと思う。
悲しみ・心の痛みをこえる機縁
今日、どんな時にお寺の本堂へと身を運んでいるだろうか。昔は子どもたちの遊び場だった。そういう場面は少なくなってしまったけれども、葬儀をお勤めし火葬した後(還骨)や法事では、お寺参りする貴重な時が与えられている。
身近な人、大切な人を亡くすことは深い悲しみである。心には激しい痛みが生じる。若くして亡くなる、突然亡くなる…嗚咽。長い闘病生活を通して亡くなり心にぽっかりと穴が開く…。悲しみの中味は一人ひとり個別のものだ。でも、自分と似たような悲しみ、どこかで自分に重なる部分を抱える痛みを経験し乗りこえた先人が、既にしてまします。 中陰のお勤めをした後、「この悲しみをまずは受け止めましょう」と申し上げたら、「とても受け止められない」と言われたことがある。そうだなあ。自分がなぜ今こうなっているのかわからない悶々とするような悲しみ。それは自分では決して受け止められない悲しみなのだ。もし、そんな悲しみに立ち止まり向き合うことができたとしたら、自分に刻まれた傷跡が仏さまによって埋木されたということ。仏さまの心が届けられた、念仏が響いた、ということだろう。
[真宗大谷派西誓寺寺報『ルート8』276号から転載]
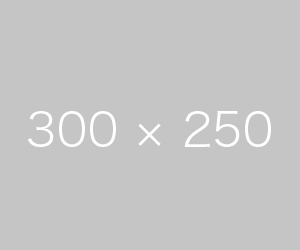
コメント