自利利他の教え
念仏の教えはいわゆるご利益信仰とは違うのだと教えられる。自分を利するだけでなく、他者をも利する自利利他円満成就の教えだからと。ご利益信仰が求めるのは、自利だけ。お金が儲かりますように、健康になりますように…。すると、自利に喜んでいる私の裏側で泣いている人がいるかもしれない。儲かったということは、損した人が必ずいる。健康を害して苦しんでいる人がいる。そんなことまで気をまわしていられない、自分のことで精一杯…。日ごろの生活感の正直なところである。
米国の大統領に再びトランプさんが就任した。米国第一、つまり自利だけでいいのだと主張し、その主張を多くの国民が受け入れている。逆にいえば他者が泣いていても、それはあくまでもその当事者の問題であって、自己責任によって解決すべし…。そんな冷たい風が吹いている。
他利と利他はどう違う
若い頃からずっと気になっていたこと、どうもすっきりとしない、わからなかったことがある。自利はいいだろう。しかし、これに対して他利ではなくて、どうして利他なのだろう。宗祖親鸞聖人の主著『教行信証』行巻で、本願力について引用しているところにはこうあるのだが、一体何を言おうとしているのか。
他利と利他と、談ずるに左右あり。もしおのずから仏をして言わば、宜しく利他と言うべし。おのずから衆生をして言わば、宜しく他利と言うべし。
『注文の多い料理店』を読み直して
最近、宮沢賢治の代表作『注文の多い料理店』を読み直した。子どもの時、変な話だなあ、少し怖いなあ、という印象しかなかった。何十年ぶりかで触れたこの童話が発するメッセージは強烈だった。
ざっくりとこういう話。料理店に入ったら、アレをして下さい、コレをして下さい、といろいろ注文される。従っているうちに自分たちが料理される側になっていることに気づき…という展開。
生きるということは、自分から何かを注文すること、自分に何かを注文されることの繰り返し。その時々でこの二つが入れ代わり立ち代わりしながら、その成果が積み重ねられていく。別の言い方をすれば、注文する・注文されるそんな人間関係の中で右往左往している。
だいたい三つのパターンに分けられる。①注文することされることが一致する②注文するがそうならない③注文されるがそうならない
この中で①が自他のどちらをも利する関係だが、よくよく考えると単に取引が成立したということ。双方満足はするが、それ以外の関係者は排除されたり、犠牲になる場合がある。ソロバン勘定がうまくいった関係は、自利利他ではなく、自利他利なのだろう。
世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない
宮沢賢治には―世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない―という有名な言葉がある。(『農民芸術概論綱要』)賢治の童話はこの願いに支えられていると言ってよい。世界全体の利、つまり、排除や犠牲されるものをも包んだ利を利他と言うのだろう。人間は、日ごろ自利と他利の関係で、大切なものを見失っている。その先に待っているのは、自分自身が食べられてしまう悲劇。この目覚めが自利利他かと。
[真宗大谷派西誓寺寺報『ルート8」275号から転載]
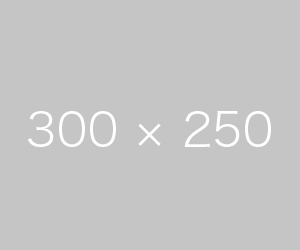
コメント