ボランティア活動する人々
連休前に、真宗大谷派奥能登ボランティアセンターが主催する「出張居酒屋」のスタッフとして活動してきた。昨年六月に出かけた時は、急用が出来てトンボ帰り。その時は、焼き豚を作って持参した。今回は煮込み料理でも…と思っていたが、参加人数が百人規模と聞き断念した。
そんな多くの人数に対して、いったいどうやって飲食物を提供するのだろう?大丈夫か?と聞いたところ、岐阜県の高山別院(飛騨御坊)からスタッフが十数人来てくれる。けんちん汁やご当地のb級グルメ、新鮮な野菜などを味わっていただける。自分たちは、獲れたてのタコを使ったタコめしを作る。三升程度ならもう何回もやっていて慣れている。ビールやお酒なども多方面から差し入れがあるらしい。
高山別院(飛騨御坊)の門徒さんに出あう
高山別院(飛騨御坊)からボランティアに来られた門徒さん。想像したより年齢層が高い。花屋をやっていてぼくは八十一歳になります、とご夫婦で。今月は本山の「春の法要」音楽法要で合唱団の一員として出仕しました、という男性は脊柱管狭窄症で腰が曲がっている。でも田んぼ仕事で鍛えた身体はてきぱき動くし、気配りがとても細やか。午前中は倒壊したお寺の本堂の災害支援作業をしていた、というから頭が下がる。そういえば、昔の古田刈にはこんな逞しいおじいちゃんおばあちゃんがおられたなあ、そして、かわいがってもらったなあ、と思い出し心がほっこりした。
東日本大震災被災者から聞いた話
高山別院スタッフの中心になって指揮を執っている末永賢治さん。話を聞くと、宮城県女川町出身でレストランを経営していたという。
3・11の時、店の中は地震でグチャグチャ。家族と車に乗って避難しようと海の方を見ると、電信柱が次々と倒れている。津波が来る!十人ほどが向こうにいる。逃げろと叫んで、自分は丘の方に走った。お店の標高は二十四メートル、でもあっという間に建物も人々も飲み込まれてしまった。三十五メートルほどの高さがあったらしい。津波が納まった後は、ご遺体を葬る作業を担った。ようやく自衛隊が救助にやってきて欲しいものを聞かた。即座に消臭剤と答えた。鼻に死体の異臭が染みついて抜けなかったから。そんな現場で格闘する毎日だった。
海の街から山の街への避難は悩んだが、家族とも相談して決断。すると、高山別院にボランティア委員会が結成され定期的に炊き出しをする門徒さんのグループが出来た。能登にもそのチームが駆けつけるようになって三回目になる。
立ち上がり、歩み出す
輪島市門前町で開催した「出張居酒屋」でけんちん汁を作っていた末永さんに、地元の女性が語りかける。
「先日、女川に行ってきました。秋にマルシエ開設を計画していて、その先行事例から学ぶための視察です」
東北も能登も被災によって大きな傷を負った。でも、その深い悲しみの中から、立ち上がり、歩み出す人がいる。一方で、日ごろ認知症の母親の介護でエンジンオイルが濁り気味の自分。ボランティアのスタッフや現地の人との出あいは、オイル交換される機会でもあった。また足を運びたいと思う。
[真宗大谷派西誓寺寺報「ルート8」278号から転載]
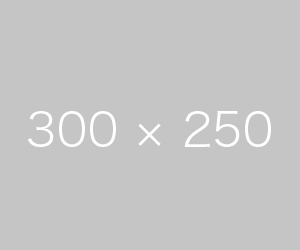
コメント