朝日新聞「声」欄の投稿
朝日新聞の「声」欄に『誰にも迷惑かけず生きられる?』というタイトルで保育士さんの投稿が掲載された。次のような内容である。
「他人に迷惑をかけてはいけない」と教えられ育てられた。こどもたちにも同じ言葉をかけてきた。でも、本当に他人に迷惑をかけてはいけないのか。誰にも迷惑かけずに生きることは可能か。…どんなに気をつけていても、どこかの誰かに迷惑をかけているはず。一人では生きていけない人間という生き物はお互いに迷惑をかけながら生きている。だから「誰かが困っている時は、進んで助けてあげてね」と伝えるようになった。迷惑をかけていないか過度に気遣うより、うまくいかない人に手を差し伸べ、協力して問題を解決する。その方がお互いに気持ちよく過ごせる。
手が合わさる
「誰にも迷惑をかけていない」と言えるのは、迷惑をかけている事実に気がついていないだけなのだろう。全世界の生きとし生けるもの皆にどうですか、これでいいですかと確かめることはできない。また、自分にとって良かれと思ってやったことが、相手にとっては逆になる事例は珍しいことではない。迷惑をかけていないはず…、少しは迷惑になるかもしれないが、まあ許容範囲だろう…。普段こんなところで日暮している。迷惑が表沙汰にならなければ、そんな曖昧でいい加減で濁った世界の中で生きている自分自身が問われることはない。
迷惑をかけていないと思っていた自分はウソ(そらごとたわごと)だった…。お粗末なことにも迷惑をかけていた、何と至らぬ愚かな自分であるか…。と気づかされて初めて手が合わさる。手を合わせるのではない。真実に呼び覚まされて、おのずと手が合わさる。頭が上がらない。この驚きの伝統が〈南無阿弥陀仏〉である。迷惑をかけて〈ごめんなさい=懺悔〉でも真実を伝えてくれて〈ありがとう=讃嘆〉との二重の意味がある、と教えられる。
手を合わせる
一度手が合わさると、今まで見えていなかった世界が明らかになってくる。迷惑ばっかりかけている。生きることは迷惑をかけること、かけ続けることではないか。だから、まずもってその事実を表明する。〈南無阿弥陀仏〉と声に出す。
更に、自ら意識して手を合わせる生活態度に努める。例えば、うまいかまずいか、高いか安いか、そんな目線をもってものを食うのではなく、食事はいただく。他のいのちをいただく。自分が生きるために犠牲になっているいのち。あちらの意思を尊重することもなく、こちらから一方的に迷惑をかけているいのちをいただく。手を合わせ〈いただきます〉と発声して始まる食事場面は、昭和のテレビドラマでは当たり前だった。しかし、最近はなかなか手が合わさらないようだ。
困っている人がいる
人間社会において代表的かつ大きな迷惑が戦争だろう。近年もウクライナに始まり、パレスチナ、イランへと戦火は拡がっている。「誰かが困っている時は、進んで助けてあげてね」と保育士さんが伝える声にどう応えたらいいのだろうか。
プーチンさん、ゼレンスキーさん、トランプさん、ネタニアフさん、アッバスさん…石破さん。手を合わせ、ご一緒に念仏申しましょう。
[真宗大谷派西誓寺寺報「ルート8」280号から転載]
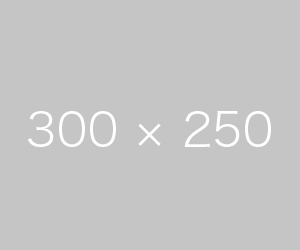
コメント