新聞連載小説「あおぞら」の問いかけ
五木寛之作「親鸞」や最近大ヒットしている映画「国宝」の原作(吉田修一作)は、新聞に連載された小説である。
今、朝日新聞に連載中の柚木麻子さん作「あおぞら」がとても面白い。一九五〇年代の東京を舞台に、縫製工場に勤務するシングルマザーが、当時は社会で認知されていなかった保育園の設立に動く。青空の下での環境から立ち上げたが、何とか屋根のある場所を確保したい。そこで、彼女は候補先としてお寺はどうだろうか、と相談をもちかける。一度断られた後、再び出会った女性僧侶との会話。
「本で読んだんです。南無阿弥陀仏って、男も女もお金持ちも貧しい人もないんですね。そこが好きだなと思いました。聞いていると、心が楽になります」…
「はい。…だから、僧侶になりたかった。平等で、人を決めつけないところが好きだったんです。でも、…」
秋季永代経におけるでも
秋季永代経のお話で、7月の寺報で取り上げた保育士さんの新聞投稿について触れた。次のような内容 (再掲載)。
「他人に迷惑をかけてはいけない」と教えられ育てられた。こどもたちにも同じ言葉をかけてきた。でも、本当に他人に迷惑をかけてはいけないのか。誰にも迷惑かけずに生きることは可能か。…どんなに気をつけていても、どこかの誰かに迷惑をかけているはず。一人では生きていけない人間という生き物はお互いに迷惑をかけながら生きている。だから「誰かが困っている時は、進んで助けてあげてね」と伝えるようになった。迷惑をかけていないか過度に気遣うより、うまくいかない人に手を差し伸べ、協力して問題を解決する。その方がお互いに気持ちよく過ごせる。
加えて、最近自分が経験したこと。ネット通販で本を購入した。郵便入れに投函したとの写真が送られたが、見当たらない。母親は知らないという。仕方なく、業者に連絡したら、再送する手配をしてくれた。翌朝、仏壇の戸を開けると、段ボールの梱包が…。注文した本は確かに送られていた。
迷惑をかけるつもりはない。でも、結果的に迷惑をかけてしまうことがある。認知症の母親の仕業だから、お金を払っているからと弁解はできても、配達員さんの信用を傷つけてしまった事実に心が痛む。手が合わさる。こんな例はよくある。迷惑をかけていることに気がつかずに、平気で生きている自分では?だから、手を合わせる。そんな話に、ある警察署長さんが会議中に怒鳴ったら、パワハラで処分されたニュースを添えた。
でも―休憩中に門徒さんが話をしている。
「迷惑かけるな、と言わんとアカンと思う」「現場仕事では優しい言葉だけでは、危険な時咄嗟の時に間に合わない」「相手との信頼関係があれば、強く言っても大丈夫なのでは」「世話になっているとは思うが、迷惑かけているとは思わん」
自分のこととして真剣に聞いてくださり、うれしかった。でも―普段の生活では情報が一方通行になりがち。なかなか聞き合うことができない。何よりも、でもと問い直すのはエネルギーが必要だ。ボーッと生きているとでもに出会えない。
報恩講【音楽法要】のでも
報恩講の【音楽法要】では、登高座中に当院独自のアレンジで愚禿悲嘆述懐和讃から六首を同朋唱和する。宗祖が仏の智慧に照らされて見えてきた自身の闇、でもの告白と言える。
浄土真宗に帰すれども
真実の心はありがたし
虚仮不実のわが身にて
清浄の心もさらになし
立派に清らかに真実を歩む人でありたい。でも、つまづきもがきウソまみれで生きている。そんなわれらを導く道がある。
〔真宗大谷派西誓寺寺報「ルート8」283号から転載]
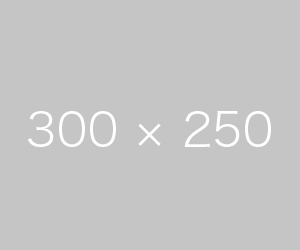
コメント